アルトコイン
アルトコイン(または、オルトコイン)とは、alternative coinの略(=altcoin)で、直訳で「(Bitcoinの)代わりとなるコイン」という意味です。一般的にビットコイン以外の仮想通貨(暗号資産)のことをアルトコインと呼びます。
特に個別のアルトコインのページについては、未作成であったり更新が追い付かず内容が古い可能性が高いのでご了承ください。
用語解説など
アルトコインも含めた仮想通貨全体でよく使われる概念・用語をまとめています。なお、これらの用語の多くは定義が曖昧であり使う人や場面によって用法が異なることが多く、次第に使われなくなったり意味が変化することもあるのでご注意ください。
本ページの内容について
アルトコインの全体像を把握しやすくするために、当サイトが独自で分類しカテゴリごとに掲載しています。これらの分類は必ずしも一般的ではなく、また実際には複数のカテゴリにまたがるようなものが多くありますが、便宜上一つのカテゴリにのみ掲載しています。表中の承認方式等の分類の説明はページ下段に掲載しています。
特に新興のアルトコインや仮想通貨関連プロジェクトには詐欺であるものが多く、過去には詐欺でなくてもネットワークへの参加者がいなくなりブロックチェーンを維持できなくなったものもあります。本ページでは信頼性を一定程度確保するために、国内の取引所で扱っているアルトコインのみを表中に掲載していますが、それらも含め一般的にアルトコインは実験的なものが多くビットコインよりも不安定な傾向がある点にご注意ください。
また、管理主体がなく透明性・永続性・耐改竄性に優れているというようなビットコインのブロックチェーンの特徴は必ずしも全てのアルトコインには当てはまりません。
開発チームが日本主体であることや日本との繋がりが深いことが理由で国内の取引所でのみ扱っているようなアルトコインも少なくなく、特に日本産の仮想通貨の中には世界の仮想通貨コミュニティから見ればかなりマイナーなものがある点にはご注意ください。参考のために規模に関わらず日本産の仮想通貨は通貨名の後ろに日本の国旗画像 をつけています。
をつけています。
①通貨・決済手段型(レイヤー1)
| 名称 | シンボル | 発行開始 | 承認方式 | ハッシュアルゴリズム | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2009年01月 | PoW型 | SHA-256 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Litecoin | LTC | 2011年10月 | PoW型 | Scrypt | ウェブサイト/ソースコード | |
| Dogecoin | DOGE | 2013年12月 | PoW型 | Scrypt | ウェブサイト/ソースコード | |
Monacoin  |
MONA | 2014年01月 | PoW型 | Lyra2REv2 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Ripple | XRP | 2012年09月 | PoA型 | - | ウェブサイト/ソースコード | |
| Stellar | XLM | 2014年07月 | PoA型 | - | ウェブサイト/ソースコード |
ビットコインに準じるような通貨や決済手段としての利用が主なアルトコインです。2014年ごろまでに誕生した仮想通貨のほとんどはこのタイプで、ビットコインのソースコードを元にコインによってマイニングのハッシュアルゴリズムなどの仕様が少しずつ変更されています。
それとは別のグループとして、一から立ち上げられたRippleとその派生のStellarもあります。
その他の代表的なコイン
②プラットフォーム型(レイヤー1)
| 名称 | シンボル | 発行開始 | 承認方式 | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEM | XEM | 2015年03月 | PoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Ethereum | ETH | 2015年07月 | PoW型→PoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Lisk※1 | LSK | 2016年05月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Neo | NEO | 2016年10月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| TRON | TRX | 2017年08月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Cardano | ADA | 2017年09月 | PoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Qtum | QTUM | 2017年09月 | PoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| IOST | IOST | 2017年12月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Vaulta※2 | A | 2018年06月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Tezos | XTZ | 2018年06月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Ontology | ONT | 2018年06月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Zilliqa | ZIL | 2019年01月 | PoW型→PoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Cosmos | ATOM | 2019年04月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| IoTeX | IOTX | 2019年04月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Algorand | ALGO | 2019年06月 | PoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Kaia※3 | KAIA | 2019年06月 | PoA型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Hedera | HBAR | 2019年09月 | DAG/PoA型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| XDC Network | XDC | 2019年09月 | PoA型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Solana | SOL | 2020年03月 | PoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| NEAR Protocol | NEAR | 2020年04月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Polkadot | DOT | 2020年05月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Avalanche | AVAX | 2020年09月 | DAG/PoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Bittensor | TAO | 2021年01月 | PoA型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Symbol | XYM | 2021年03月 | PoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Solar | SXP | 2022年03月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Sei | SEI | 2022年05月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Flare | FLR | 2022年07月 | DAG/DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
Japan Open Chain  |
JOC | 2022年08月 | PoA型 | ウェブサイト/ソースコード | |
Oasys  |
OAS | 2022年09月 | PoA/DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Aptos | APT | 2022年10月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| Sui | SUI | 2023年05月 | DAG/DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード | |
| UPCX | UPC | 2024年10月 | DPoS型 | ウェブサイト/ソースコード |
スマートコントラクトやトークン発行が主な機能であるプラットフォーム型のアルトコインです。最も代表的なEthereum(イーサリアム)の登場後に、Ethereumとの対抗または併用を目指して多くのブロックチェーンが立ち上げられています。
ブロックチェーン上に直接スマートコントラクトを乗せるというよりは、DAppsを構築するサイドチェーンを乗せることを前提としたレイヤー0と呼ばれるCosmosやPolkadotもこちらに含めています。
また、汎用的なプラットフォームに限らず、分散型ID等に特化したOntologyやゲームに特化したOasys、IoT分野に特化したIoTeXなど、複数のDappsをのせることを前提としたプラットフォーム的ブロックチェーンであればこちらに分類しています。
※1 Liskは2024年5月以降ブロックチェーンを停止し、Ethereum上のレイヤー2としてのLisk(LSK)と新たなレイヤー1のブロックチェーンのKlayr(KLY)に移行しています。
※2 Vaultaは2025年5月にEOSからVaultaにリブランディングされました。(ネイティブトークン(A)も新しく発行されたが、ブロックチェーンはそのままのリブランディングで旧EOSトークンもそのまま維持)
※3 Kaiaは2024年8月にLINE社発行のブロックチェーンFINSCHIAと統合した際に、KlaytnからKaiaへ名称変更されました。
③ハードフォークコイン
| 名称 | シンボル | 分岐開始 | 承認方式 | 分裂元コイン | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 2016年07月 | PoW型 | Ethereum | ウェブサイト/ソースコード | |
| Bitcoin Cash | BCH | 2017年08月 | PoW型 | Bitcoin | ウェブサイト/ソースコード | |
| Bitcoin SV | BSV | 2018年11月 | PoW型 | Bitcoin Cash | ウェブサイト/ソースコード |
コミュニティの対立などによりブロックチェーンも含めたプロジェクトが分裂(ハードフォーク)したものです。基本的な性質は分裂前の仮想通貨に準じます。
分裂前の仮想通貨と分岐時点では全く同じブロックチェーン(取引履歴)であるため、分岐時点のコインの残高を共有することになり、利用者は実質的に2種類のコインを保有することになります。
④レイヤー2/サイドチェーン
| 名称 | シンボル | 発行(稼働)開始 | 分類(承認方式) | 基盤チェーン | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Counterparty | XCP | 2014年01月 | レイヤー2 | Bitcoin | ウェブサイト/ソースコード | |
| Polygon | POL※ | 2019年04月 | サイドチェーン(DPoS型)/レイヤー2 | Ethereum | ウェブサイト/ソースコード | |
| Shiba Inu | SHIB | 2020年07月 | レイヤー2 | Ethereum | ウェブサイト/コントラクト | |
| Arbitrum | ARB | 2021年05月 | レイヤー2 | Ethereum | ウェブサイト/コントラクト | |
| BOBA Network | BOBA | 2021年09月 | レイヤー2 | Ethereumほか | ウェブサイト/ソースコード | |
| Immutable | IMX | 2021年10月 | レイヤー2 | Ethereum | ウェブサイト/コントラクト | |
| Optimism | OP | 2022年04月 | レイヤー2 | Ethereum | ウェブサイト/ソースコード | |
| CyberConnect | CYBER | 2023年08月 | レイヤー2 | Ethereum | ウェブサイト/ソースコード | |
| Lisk | LSK | 2024年05月 | レイヤー2 | Ethereum | ウェブサイト/ソースコード | |
| Efinity token | EFI | 2021年05月 | サイドチェーン(DPoS型) | Polkadot | ウェブサイト | |
| Astar | ASTR | 2022年01月 | サイドチェーン(DPoS型) | Polkadot | ウェブサイト/ソースコード |
元チェーンのスケーラビリティ(取引処理能力)向上や機能の拡張を行うためのプロジェクトです。ブロックチェーンを別に立ち上げるものをサイドチェーン、そうでないものをレイヤー2と区分しています。
※Polygonのネイティブトークンは2024年9月にMATICからPOLへ変更されました。
⑤DAppsトークン/その他独自トークン
| 名称 | シンボル | 発行開始 | 主な利用チェーン | 概要 | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Attention Token | BAT | 2017年05月 | Ethereum | ブラウザ内トークン | ウェブサイト/コントラクト | |
| OMG Network | OMG | 2017年07月 | Ethereum | 旧レイヤー2トークン(BOBAへ移行済) | コントラクト | |
| Chainlink | LINK | 2017年09月 | Ethereum | 分散型オラクル | ウェブサイト/コントラクト | |
| Decentraland | MANA | 2017年09月 | Ethereum | メタバースプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Render Token | RENDER | 2017年10月 | Ethereum→Solana | 分散型クラウドレンダリング | ウェブサイト/コントラクト | |
| Enjin Coin | ENJ | 2017年11月 | Ethereum | NFTプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Sky※1 | SKY | 2017年11月 | Ethereum | ステーブルコインUSDS(旧DAI)発行DAO | ウェブサイト/コントラクト | |
Cosplay Token  |
COT | 2018年03月 | Ethereum | コスプレイヤーへの投げ銭トークン | ウェブサイト/コントラクト | |
| Livepeer | LPT | 2018年04月 | Ethereum | 分散型ビデオストリーミングプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| BORA | BORA | 2018年07月 | Klaytn | GameFiプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Chiliz | CHZ | 2018年10月 | Ethereum | スポーツのファントークン | ウェブサイト/コントラクト | |
| Theta Network | THETA | 2019年03月 | 独自ブロックチェーン | 分散型ビデオストリーミングプラットフォーム | ウェブサイト/ソースコード | |
| Artificial Superintelligance Alliance | FET | 2019年03月 | Ethereum | 分散型AIエコシステム | ウェブサイト/ソースコード | |
DEAPCoin  |
DEP | 2019年08月 | Ethereum | エンターテイメントプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| The Sandbox | SAND | 2019年10月 | Ethereum | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Toncoin | TON | 2019年11月 | 独自ブロックチェーン | Telegram(メッセージングアプリ)内トークン | ウェブサイト/ソースコード | |
JasmyCoin  |
JASMY | 2019年12月 | Ethereum | IOTプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Gala | GALA | 2020年09月 | Ethereum | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Axie Infinity | AXS | 2020年10月 | Ethereum | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Filecoin | FIL | 2020年10月 | 独自ブロックチェーン | 分散型ストレージ | ウェブサイト/ソースコード | |
| The Graph | GRT | 2020年12月 | Ethereum | 分散型データ検索システム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Mask Network | MASK | 2021年02月 | Ethereum | 暗号化メッセージングプロトコル | ウェブサイト/コントラクト | |
Palette Token  |
PLT | 2021年05月 | 独自ブロックチェーン(PoA型)/Ethereum | NFTプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト/エクスプローラー | |
| Cratos | CRTS | 2021年06月 | Ethereum | 投票プラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト | |
FC Ryukyu Coin  |
FCR | 2021年08月 | Ethereum | サッカーチームのファントークン | ウェブサイト/コントラクト | |
Gensokishi Metaverse  |
MV | 2021年12月 | Polygon | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
ROND Coin  |
ROND | 2021年12月 | Polygon | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| ApeCoin | APE | 2022年02月 | Ethereum | Web3.0関連コミュニティへのサポート | ウェブサイト/コントラクト | |
| MARBLEX | MBX | 2022年03月 | Klaytn | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
Skeb Coin  |
SKEB | 2022年07月 | Ethereum | クリエイターコミッションサービス内トークン | ウェブサイト/コントラクト | |
XENO Governance  |
GXE | 2022年09月 | Ethereum | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
Nippon Idol Token  |
NIDT | 2022年11月 | Ethereum | アイドルグループ関連プロジェクト | ウェブサイト | |
FiNANCiE Token  |
FNCT | 2023年02月 | Ethereum | クラウドファンディングプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト | |
TSUBASA Governance Token  |
TSUGT | 2023年02月 | Polygon | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Pepe | PEPE | 2023年04月 | Ethereum | ミームコイン | ウェブサイト/コントラクト | |
Oshi Token  |
OSHI | 2023年09月 | Polygon | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
| Memecoin | MEME | 2023年10月 | Ethereum | Web3コミュニティプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト | |
ELF Token  |
ELF | 2024年02月 | Palette Chain(PLT) | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
Blood Crystal  |
BC | 2024年02月 | Polygon | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
SNPIT TOKEN  |
SNPT | 2024年04月 | Polygon | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
Brilliantcrypto Token  |
BRIL | 2024年05月 | Polygon | ブロックチェーンゲーム | ウェブサイト/コントラクト | |
NOT A HOTEL COIN  |
NAC | 2024年08月 | Ethereum | 別荘シェアリングプラットフォーム | ウェブサイト | |
| Neiro Ethereum | NEIRO | 2024年08月 | Ethereum | ミームコイン | ウェブサイト/コントラクト | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2025年01月 | Solana | ミームコイン | ウェブサイト/コントラクト | |
Fanpla  |
FPL | 2025年04月 | Polygon | Web3ファンクラブプラットフォーム | ウェブサイト/コントラクト |
特定の用途(DApps)に特化して作られている主にブロックチェーン上で発行されているトークンです。表中では国内取引所で取扱いされているEthereumトークンとして記載しているものがほとんどですが、実際には複数のブロックチェーン上でトークンが発行されていたり、独自のブロックチェーンを運用しているものもあります。
※1 2017年11月に発行されたMakerDAO(MKR)が元のプロジェクトでしたが、2024年9月に発行されたSkyへと移行されました。
⑥ステーブルコイン
| 名称 | シンボル | 発行開始 | ペグ対象 | 利用チェーン | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dai | DAI | 2017年12月 | 米ドル | Ethereum | ウェブサイト/コントラクト | |
| USD Coin | USDC | 2018年9月 | 米ドル | Ethereum | ウェブサイト/コントラクト | |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 2018年11月 | ビットコイン | Ethereum | ウェブサイト/コントラクト | |
Zipangcoin  |
ZPG | 2022年02月 | 金 | 独自プライベートブロックチェーン | ウェブサイト | |
Zipangcoin Silver  |
ZPGAG | 2023年07月 | 銀 | 独自プライベートブロックチェーン | ウェブサイト | |
Zipangcoin Platinum  |
ZPGPT | 2023年07月 | プラチナ | 独自プライベートブロックチェーン | ウェブサイト |
特定の資産(法定通貨・商品・仮想通貨など)の価格と連動して価格が変化するトークンです。常に1コイン=1ドルの価値を保つ米ドルのステーブルコインがよく使われており、国内取引所での取扱いがないため表中には記載していませんが、Tether(USDT)が最も有名です。
その他の代表的なコイン
 Tether(USDT) - 米ドル
Tether(USDT) - 米ドル
⑦取引所トークン
| 名称 | シンボル | 発行開始 | 利用チェーン | 取扱取引所 | 発行企業 | リンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAIF  |
ZAIF | 2016年04月 | Counterparty→Ethereum/Symbol | Zaif | テックビューロ株式会社 | ウェブサイト/コントラクト(ETH) | |
COMSA  |
CMS | 2017年11月 | Ethereum/NEM/Symbol | Zaif | テックビューロ株式会社 | ウェブサイト/コントラクト(ETH) | |
CAICA Coin  |
CICC | 2016年10月 | Counterparty→Ethereum | Zaif | 株式会社CAICA DIGITAL | ウェブサイト/コントラクト | |
Fisco Coin  |
FSCC | 2016年10月 | Counterparty→Ethereum | Zaif | 株式会社フィスコ | ウェブサイト/コントラクト | |
NCXX Coin  |
NCXC | 2016年10月 | Counterparty→Ethereum | Zaif | 株式会社ネクスグループ | ウェブサイト/コントラクト | |
c0ban  |
RYO | 2016年12月 | 独自PoWブロックチェーン | c0ban取引所 | 株式会社LastRoots | ウェブサイト/ソースコード | |
| OKB | OKB | 2019年04月 | 独自ブロックチェーン(Ethereum上のLayer2) | OKCoinJapan | OKX | ウェブサイト/エクスプローラー | |
| Build N Build | BNB | 2017年06月 | 独自ブロックチェーン | Binance | Binance | ウェブサイト/エクスプローラー |
取引所の運営企業が発行・運用する取引所トークン、またはその関連企業が発行する企業トークンなどをここに分類しています。
日本でもサービスを開始した世界でも最大手の取引所Binanceが発行するスマートコントラクトプラットフォームでもあるBNBが最も有名です。
アルトコインの仕様
以下のような点がビットコインと異なることがあります。
承認方式(コンセンサスアルゴリズム / Consensus Algorithm)
取引の承認を行う方式です。各アルトコインが独自の名前を付けることが多くすべて区別して扱われることが多いですが、本ページでは各プロジェクト公称のコンセンサスアルゴリズムによらず、理解しやすいように内容によって5つの型に分類しています。複数の方式を同時に採用するハイブリッド型のものも存在します。
技術者向けというよりは一般向けに、かなり大雑把な分類となっているのでご注意ください。さらにカジュアルに理解するのであれば、マイニングにより報酬が貰えるPoW型、ステーキング/デリゲートにより報酬がもらえるPoS型/DPoS型、その他の3つに大別することができます。
PoW(Proof of Work)型
ビットコインが採用している方式で、コンピュータによる計算の競争により承認を行い、計算力が高ければ高いほど承認確率・採掘確率が上がるものです。誰にでも承認には参加できることで、非中央集権性を保ったままセキュリティを高くできるのが強みですが、エネルギー・電力消費が大きく取引処理能力は低いのが欠点です。
開始時に中央集権的な組織がコインを配布せず、発行量ゼロからスタートできるのも他の方式にはない唯一の特徴です。
承認者を選ぶ過程にのみPoWが使われており合意形成の段階ではPoWが利用されないZilliqaも、実質的にマイニングが可能なアルトコインとして例外的にPoW型に分類しています(Zilliqa2.0からはPoS型に以降)。
ハッシュアルゴリズム / Hash Algorithm: Proof of Workで使われているハッシュ関数のことです。ビットコインではSHA-256が利用されています。アルゴリズムによって、マイニングの効率や消費電力が変化します。
Difficulty調整 / Difficulty retarget: Difficulty(採掘難易度)の調整方法です。基本的に前のブロックを発見するまでの時間、言い換えればマイニングに投入されたコンピュータの計算速度によってビットコインでは2016ブロック(約2週間)毎に調整されます。アルトコインではブロック数が異なっていたりもっと複雑な計算によって調整を行っているものもあります。
PoS(Proof of Stake)型
計算力のPoWに対してStake(=掛け金)を競争の材料とするもので、マイニングにつぎ込むコインの量が多ければ多いほど承認確率が上がります。一般的にPoSにおけるマイニングは「ステーキング」と呼ばれます。ステーキングにおいては、単純な保有量だけでなく保有期間またはステーキング期間も承認過程で考慮されるものが多いです。
膨大な計算量をつぎ込む必要がないので、PoWに比べてエネルギー消費が少なくマイニング速度・取引処理能力が高くなるのが特徴です。資産多く持っているほど稼ぎやすいために富の集中につながりやすいことや、ステーキングによりコインの流動性が低下しやすいことなどが欠点とされています。
PoSの派生型は多く、コイン量だけではなく取引量も考慮されるNEMのProof of Importanceなども、ここではPoS型として分類しています。
DPoS(Delegated Proof of Stake)型
DPoSはコインの保有者が保有量に応じた承認者を選ぶための投票権をもち、承認者として選ばれた一定数のノードが承認を行う方式です。承認を行う代表者を投票により選ぶので、間接民主制的なシステムとも言えます。投票を行った承認者がブロックを承認すると投票分に応じて投票者も報酬をもらえることが多く、その投票のことを「デリゲート」または「ステーキング」と呼びます。
誰でも承認作業に直接参加できるPoSに対して、プロトコルで承認者の人数が一定と定められている点が大きく異なります。PoWやPoSでもマイニングプールやステーキングプールと呼ばれる一部の代表者が承認を行うシステムがありますが、それらは競争及びランダム性がありまたプールに参加せず個人でも直接マイニングすることが可能です。しかし、DPoSではブロックを生成しようと同時に競争することはなく選ばれた承認者が持ち回りで承認していきます。
一定の人数でただ順番に承認を行っていくのでPoSよりもさらに取引処理能力・速度が高いのがメリットですが、人数が決まっている分代表者の選出方法によっては中央集権的になりやすいことが欠点と言えます。
※黎明期のPoSは、PoWと同様に1ブロックごとにハッシュ計算によりブロック生成を競うのが普通でしたが、その後のPoS型は処理能力を上げるためにDPoS型のシステムに近づいていて境界が曖昧になっており、承認者はステーキング量に応じた単純な確率などによって選ばれ、ブロック生成の段階では特に競争を行わないものが多くなってきています。そのため、承認者の人数に制限を設けるなど明らかにDPoSに近いと判断したもの以外は、PoS型と公称しているものはPoS型に分類しています。
PoA(Proof of Authority)型
PoAは、承認者の候補が現実の身元を明らかにして、その評判を元に承認者を決定する方式のことを通常指しますが、ここでは定義を広げ特定の管理主体ないし不特定多数が一定数の特定の承認者を選ぶ方式を広くPoA型として扱っています。承認者になるために特定の管理主体の許可が必要か、または許可が必要なくても資産のステーキング(デリゲート)による投票過程がない点をDPoS型と区別しています。
DPoSと同じように取引処理能力が高いのが特徴ですが、中央集権的になりがちなのが欠点です。
管理主体があるプライベートブロックチェーンで通常使われるアルゴリズムをこちらに分類しているほか、不特定多数が承認者を選ぶRippleやStellarにおけるFBAと呼ばれるアルゴリズムもここに分類しています。
DAG(Directed Acyclic Graph)型
有向非巡回グラフと訳される、コンセンサスアルゴリズムではなく単純なデータ構造を表す言葉です。ブロックチェーンとよく対比され、取引のまとまり(=ブロック)ごとに承認作業を行うブロックチェーンに対し、一つの取引ごとに並列で承認作業を行う方式をここではDAG型として分類しています。
なお、DAGとブロックチェーンを併用したり、あるいはここには分類していませんがブロックチェーンでも並列で承認を行うものもあります。
ブロックごとではなく取引ごとに並列で承認が行われるため、取引処理能力・速度が最も高い方式ですが、どのようにしてセキュリティ及び非中央集権性を両立させるのかが課題となっています。
発行上限 / Total Supply
コインの総発行量のことです。Bitcoinのように発行量に上限があるデフレ通貨と、Dogecoinのように発行量に上限のないインフレ通貨の大きく二つに分類されます。
ブロック報酬 / Block Reward
一つのブロックをマイニング・承認した時に承認者が報酬として得られる新規に発行される仮想通貨の量のことです。これはそのまま通貨の発行速度、インフレ率に直結しています。承認者の報酬としては、新規発行されるブロック報酬に加えて取引手数料も貰える場合が多いです。
通貨の価値低下を防ぐためほとんどの仮想通貨は、徐々に発行量が少なくなっていく形式をとっています。最初から全て発行済みで実質的にブロック報酬がゼロのものも存在します。
ブロック生成間隔 / Block Time
一つのブロックがブロックチェーンに組み込まれるまでの時間で、これはそのまま取引の承認完了時間となり、取引処理能力の高さに繋がります。よくビットコインの取引時間は約10分と言われますが、それはこのブロック生成間隔が約10分に設定されているためです。
一般的に、承認完了時間を短くしようとすると、セキュリティ(特に安定性)または非中央集権性が失われる傾向にあるため、取引処理能力と非中央集権性とセキュリティの3つをいかに高い水準で保つかがアルトコインの設計の大きな課題となっています。
アルトコインの価格
仮想通貨はものによって供給量や最小単位が全く異なるため、単純な1コインあたりの価格でそれぞれの価値を測ることはできません。そこで、コインの単価×供給量で表される時価総額(Market cap)が一つの比較指標としてよく用いられます。
また、本ページの表には国内取引所で取扱いのあるアルトコインしか掲載していません。日本の取引所では取扱いのために審査があり時間もかかる関係上、取扱う種類に偏りが見られ必ずしも取引されているアルトコインの価値が高いという訳ではありませんので、以下のような時価総額の一覧を表示するサイトを一つの参考にすることをおすすめします。
アルトコインのウォレット
Ethereum及びEthereum上のトークンを管理するMetamask が最も有名で利用者も多いです。
が最も有名で利用者も多いです。
ただし、Metamaskはブラウザ拡張機能やモバイルアプリとして用意されており、それ自体のセキュリティは高くないため、多額の保管には基本的にハードウェアウォレットをおすすめします。ハードウェアウォレットはEthereum以外のブロックチェーンにもかなり広範囲に対応している点でもメリットがあります。
その他、各公式サイトに専用のウォレットへのリンクが掲載されています。同時に複数種類の仮想通貨を保管できるウォレットは便利な一方、それぞれのアルトコインで別々のウォレットを使うことは分別保管になりセキュリティ面では好ましいです。個人の価値観や保管額などに応じてどのように保管するか選択すると良いでしょう。
アルトコインの入手
取引所
国内取引所
海外取引所
国内取引所は審査がある関係上、一部の上位のアルトコインが取り扱えないほか、伸び始めたばかりのアルトコインの取引が出来るまでに時間がかかるデメリットがあります。その点、アルトコインの売買では海外取引所の方が便利です。
ただし、法規制が緩い分安全性は国内取引所には劣るため、本ページでは具体的な取引所名の紹介は行っていません。自分で調べることのできる方のみが利用することをおすすめします。
分散型取引所(DEX)
ブロックチェーン上の取引所でUniswap が最も有名です。
が最も有名です。
取引所に資産を送金し預けなくても、ウォレットから直接取引所に繋げるので従来の取引所に比べ安全性が高いです。初心者にとってはハードルが高いので、ウォレットの扱いに慣れている方に利用をおすすめします。
Uniswap以外の分散型取引所の出来高リストは以下のようなサイトから確認できます。
マイニング・ステーキング
PoW型の仮想通貨は専用機器やGPUによりマイニングでコインを入手することが可能です。PoS型またはDPoS型の仮想通貨は、既にコインを持っていればステーキングによりコインを増やすことが可能です。
その他
新規のプロジェクトが始まる前や何らかの節目のときには、特定の仮想通貨の残高に応じてトークンが配布されること(エアードロップと呼ばれる)があります。その他、プロジェクトが分裂しブロックチェーンが分岐するかたちのハードフォークが行われると、分岐前の仮想通貨を持っていた場合、ハードフォーク後のコインを入手することになります。
アーカイブ
過去に個別ページを作成していたアルトコインやビットコイン2.0と呼ばれていたものを一覧で掲載します。
 Peercoin(PPC) - 最初のPoS採用仮想通貨
Peercoin(PPC) - 最初のPoS採用仮想通貨 Namecoin(NMC) - 分散型DNS(PoWブロックチェーン)
Namecoin(NMC) - 分散型DNS(PoWブロックチェーン)- その他のアルトコイン
 Nxt(NXT) - 最初の100%PoS型仮想通貨
Nxt(NXT) - 最初の100%PoS型仮想通貨 BitShares(BTS) - 最初のDPoS型仮想通貨
BitShares(BTS) - 最初のDPoS型仮想通貨 Omni - ビットコインのレイヤー2技術
Omni - ビットコインのレイヤー2技術Colored Coins - ビットコインのレイヤー2技術
- Open Transactions - ビットコインのレイヤー2技術
 MaidSafe - 分散型インターネット
MaidSafe - 分散型インターネット Storj - 分散型クラウドストレージ
Storj - 分散型クラウドストレージ Swarm - クラウドファンディングプラットフォーム
Swarm - クラウドファンディングプラットフォーム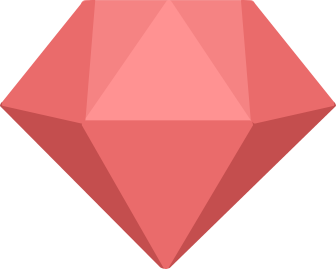 Gems - 分散型メッセンジャーアプリ
Gems - 分散型メッセンジャーアプリ
最終更新日: 2026年02月01日
コメント欄
コメントシステムを試験的に変更し、メールアドレスの入力やSNSからのログインを廃止しました。投稿後5分以内であれば編集や削除が可能です。その後に削除したいコメントがあれば依頼していただければこちらで削除いたします。
質問については出来る限りお答えしていますが、個人が運営している関係上対応の遅れや見逃し等限界もあるのでご了承ください。

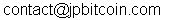 または、
または、